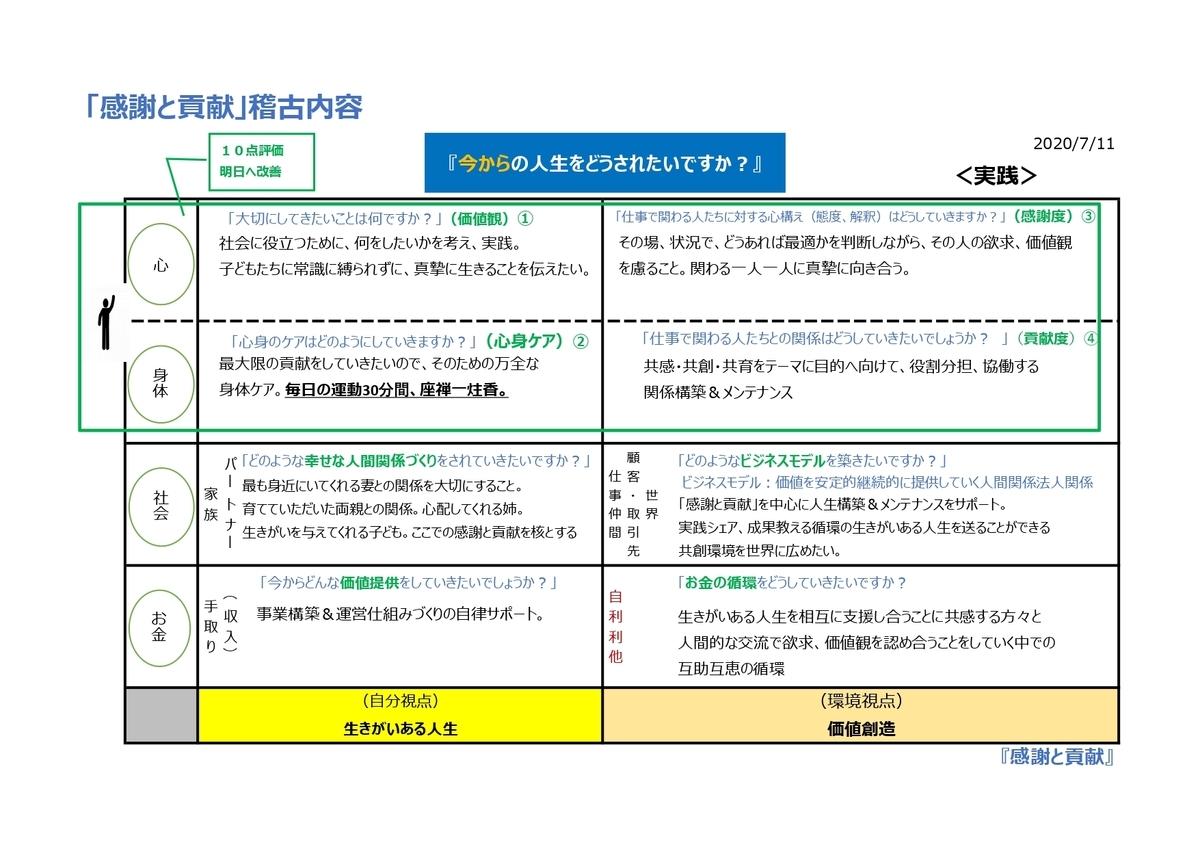「感謝と貢献」稽古第194日
『まちの健康ステーション』
(健康経営=生き方働き方創造)
健康経営という
企業が従業員の健康増進をサポートすることで
生産性向上・企業価値向上につながっていくとの仮説を立てて
企業経営に取り入れている会社が少しずつ増えてきている。
しかし、中小零細企業といわれる多くの会社では、
健康経営優良法人認定制度での認定を得ることでのイメージアップのために
要件を満たすためにしているところが大半であるという事実もある。
経済産業省のHPからの抜粋であるが、
健康経営優良法人認定制度は、
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
社会的な評価を受けることが健康経営をやる目的になっているところが多い。
健康経営優良法人認定制度をサポートすることをビジネスにするところも多くなってきているが、大半が社会的な評価が得られるように、認定取得申請サポートするのみに終わることは、日本にとって非常に損失になる。
本来の健康経営が意図している
生産性向上・企業価値向上につながっていくとの仮説を立てて
企業経営を持続可能なものにすることを実現するためには、
価値創造活動をサポートする仕組みが必要であると思う。
そのためにも、共創事業プロジェクト。
中小零細企業にとって、
生産性向上・企業価値向上をもたらすためには、
価値創造プラットフォームを自社で活用できる仕組みをつくることで、
それが実現できると思っています。
このプラットフォームを活用するための費用や人的な負担とならないためには、
応援したい人、企業、地域のいずれかを決めて、
応援のエネルギーを中心に据えてプロジェクトを立ち上げ。
参加する(会社経営者)(個人事業主)(会社員)は、
各々の立場で学びと成果を得られるように、
目標設定:健康人生(生き方働き方創造)、お金の流通
これからの社会保障が薄くなっていく中での人生100年時代を
目標設定の力により生まれる道を拓くエネルギー。
そして、プロジェクトでの交流による結合から生まれる価値創造。
価値創造プラットフォームの起点として、
顧客創造できるための強力なマーケテイングサポート。
マーケット(市場)創造実践シェア共有を出来る環境。
共通言語・共通認識を得られることで
再現性のある自社で活用できる価値創造プラットフォームにするためにも
まずは身近な応援したくなる方々と共に共存共栄コミュニティを構築運営
ピーター・F・ドラッカーが提言していた現代は知識社会。
ドラッカー研究( https://creatingvalue.hatenablog.com/)
から引用させて頂くと、
連携により生命を持つ
知識は他の知識と結合したとき、爆発的な力を発揮する。
知識社会では、知識が組織によって活用されることで、社会的な意味を獲得する。専門知識を有機的に連携させる場、結合させる場が、組織である。組織とは、知識の培養器である。
また組織とは、人が目標に向かってともに働く場と、それに伴うつながりの全体を指す。「組織」というより、「ネットワーク」と読んだほうがふさわしいこともある。
現代のプロフェッショナルは緩やかにネットワークを組み替えながら、常に新しいプロジェクトで成果をあげていく。フリーランスで活動する人同士の組織も、近年ではめずらしくない。
組織と知識
先進社会においてさえ、組織の側が人の遇し方を知らないことは通常である。同時に、個人の側が組織を通して成果をあげる方法を知らないことも通常である。なぜかといえば、組織というものが最近の発明だからである。
知識社会にあって、組織と知識はともに立ち、ともに倒れる相補的関係にある。知識が中心となる社会は、必然的に組織社会である。脱大組織はあっても、脱組織はない。
1960年代あたりまでは、知識の専門化は部分的にしか進んでいなかった。戦前戦後の先進国の経済にあって、成長とは工業化を意味した。人々が従事する仕事の多くは単純肉体労働であり、同じことを継続的に行うことが何よりも重視された。大規模な生産システムを構築し、それを継続しさえすれば、工業を中心とする社会は半ば自動的に成長軌道に乗ることができた。
だが、工業化には自ずと限界がある。工業は投入する資源価格の影響を受ける。また、商品が社会の隅々にまで行き渡ると、やがて消費も飽和点を迎える。さらには1972年にローマクラブのレポート『成長の限界』が示したように、環境問題という制約が顕在化する。やがては物質文明のピークに時代は逢着することになった。
<健康経営優良法人認定制度とは>




健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
本制度では、規模の大きい企業や医療法人等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業や医療法人等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。